|
蹴鞠
いつものように佐為の屋敷の簀子は午後の日の光がやわらかく差して居心地が良い。
「光、蹴鞠をしましょう!」
「え〜、やだよぉ」
光は額にしわを寄せ眉を下げてそう言った。
「どうして?光。最近、私が誘うといつも断るじゃないですか。あなたは最近運動足りないのじゃないですか?育ち盛りなんだから、身体動かした方がいいですよ。じゃないといつまでたっても、私の背なんて追い越せません」
佐為はどうやら、佐為なりに光のことも思って誘ってるらしかった。
「そんな心配いらないよ。オレ、運動不足なんかじゃないよ。お前が昇殿してる時とか、わざわざ大内裏の外まで出て、検非違使庁に行ってることだってあるんだぜ。そういうときに、他のやつらと剣の手合わせとか、弓の練習とかしてるし。・・・・・それになー。オレが小さいのはお前のせいなんだからなっ」
「はぁ・・・・?」
「お前がいつも心配掛けるから、オレは背が伸びないんだよ」
「光、私、あなたの背を縮めるほど、心配かけてますか?」
「ち、縮めるとはなんだよ。縁起でもないこと言うなよな、もぉ!」
光は膨れ面である。
「じゃあ、光、さぁ蹴鞠をしましょう」
尚も佐為は明るく光を誘い続ける。
「や・あ・だ」
「光ぅ〜っ。光の意地悪!。光のけち!」
なんだよ、こいつはも〜〜。いい大人のくせに!オレの為とかいって自分がやりたいんじゃん。
「もう仕方ないなぁ。じゃぁちょっとだけな」
光は佐為の無邪気な顔を見ると、やはり断れない。拒否し続けたら、こいつの寂しい顔を見ることになる。たとえ、それが蹴鞠を断られて拗ねた顔であっても、たかが、そんなことであっても、嫌・・・だった。そう、嫌だ。佐為のしょぼんとした顔は見たくない。仕方なしに腰をあげた。
簀子から繋がる階を下りて、庭に出る。遣り水の跡らしき窪みだけが通り、池の水は底の方に雨水がたまっている程度である。
池に渡した、太鼓橋は色も褪せ、さびれた様子を呈していた。そして一面の薄。
草や薄のあまり生えていない、簀子のすぐ傍のところで光は鞠を沓先にあてがった。光はいつも佐為の家に居る時は狩衣か水干を着ていた。今日は狩衣より更に動きやすい水干を着ている。光が好んで着る衣である。
「よーし」
「はい!光、どーぞ!」
佐為は手を上げてはしゃいでいる。
「いくぞ、それっっと」
光は勢いよく器用に鞠を蹴り上げた。鞠は二人の頭上にまで跳ね上がり、弧を描いてまるで吸い寄せられるように佐為の足元へとゆっくり落ちていく。
佐為はちょうど右足の上に落ちてきた鞠をなんとか落とさぬように2回蹴り上げ、3回目に光の方へ蹴り上げた。
この時である。光が気合を入れなければいけない瞬間は。光の目は真剣だった。佐為の沓先の動きに神経を集中させる。
そして次の瞬間、走る。
た、た、た、たっ。よし!読みきったぞ。ポーン。
「それっ」
光は鞠の飛んでいった方向へ小走りに数歩走ったかと思うとまた上手に鞠を蹴り上げ、2回ほど自分の頭上に高く飛ばす。そして向きを整え直した光の足元に落ちてきた鞠をまた佐為の足元へと、弧を描いて蹴り上げてやる。
佐為は先ほど立っていた位置とまったく変わらない位置でまた鞠を受け止め、蹴り返す。
そしてまた光は走る。たったったった。ポーン。
たったったった。ポーン。
「わー、光。楽しいですねえ」
佐為は相変わらず、一歩もその立ち位置を移動することなく、光の蹴り返す鞠を蹴っている。
しかも続けるうちに佐為はだんだん、蹴る回数が減っていった。時には1回目で蹴り返してしまう。ルール違反だが佐為は気にする様子もない。
運動量の差は歴然だった。こんなラリーが数十回は続いただろうか。
さすがに集中力が鈍ってくる。
「はぁ、はぁ、はぁ。も、もうだめだぁ。わわわわ」
光は鞠の落下地点を読みはぐり、鞠に初めて土が付いた。
「あ〜あ。落ちちゃった」
「あらら、せっかく続いていたのに、残念でしたね」
佐為はのん気に笑っている。
「ささ、今一度」
佐為は落ちた鞠を今度は自分から蹴り上げた。
「わっ。ちょっと待ってよ!」
あわてて、光はまた走る。こうしてまた数十回のラリーが鞠が落ちるまで続き・・・と、それがさらに何回か繰り返された。さすがの光ももうへとへとである。
「たんま!オレ、もうだめ、休憩だぞ!佐為」
二人は階段を昇り沓を脱いで簀子に上がった。
「どう、ちっとは楽しかった?おれもう疲れちゃったよ。佐為、喉渇いた」
「え、もう疲れちゃったんですかぁ?私はまだ平気ですよ」
佐為は相変わらず機嫌が良さそうに笑っている。
「そりゃ、おまえは疲れないだろうさっ。!」
「ああ、光とだけは、蹴鞠もこのように楽しめるのに・・・もうおしまいなんて残念」
「なに?それどうゆうこと」
「だって、他の人とやっても、こうは長く続かないので、つまらないのです」
「それさあ・・・。おまえどーしてだか分かってんのかぁ?」
「ええ・・・分かってますよ、それくらい。ふんっ。でも上手な光とやると私の蹴った鞠をちゃんと蹴り返してくれるので、楽しいんです」
「なんだよ、おまえ分かってて、いつもオレ誘ってんのかぁー」
光は少し呆れ顔である。
「わー、それより光、よく見るとすごい汗。何か飲み物を持ってこさせましょう。だれぞ!光に冷たい飲み物を!」
佐為は屋敷の奥に向かって呼びかけた。すると、一人の中年の女房が飲み物を簀子に運んでくる。
「佐ー為ー。暑くなっちゃった。オレ。これ脱いでいい?」
光は飲み物を一気に飲み干すと簀子に仰向けに横になった。
「え?」
「暑いよ、ダメ」
そう言って、屋敷の主人の答えを待たずに着ていた水干を脱いでしまった。
「ちょっとそいつも貸してよ」
そう言って佐為の扇を取り、単の着物と、指貫袴だけになった光は仰向けになって扇子を扇いでいる。
「私が扇いであげますよ、ほら」
佐為は光から扇を取り上げ、大の字になっている光の傍らに座って扇いでやる。
「あ〜、涼しい」
「光、大丈夫?汗が冷えたら、風邪引いてしまいますよ。早く、衣を着なさい」
佐為は、汗の伝う首の傍、光の単の襟元に指先で軽く触れてみた。
「光。着物がびっしょりです!これでは本当に風邪ひいてしまいますよ。
それも脱いだ方がいいようですね」
「オレ、着替え持ってないよ。ぶるっ」
熱した体が冷めてくると今度は光は急に寒くなってきた。秋も深まりつつある。日も傾いてきていた。
「じゃぁ。こちらに来なさい、光。何か貸してあげるから」
そう言って、佐為は板敷きの簀子から一段高くなっている廂の間へ入っていった。廂の間は簀子との間のしとみ戸も開け放たれ、御簾が高く巻き上げられていたので光りが射し込み明るかった。さらにその奥には花鳥柄の障子があり、その障子は開け放してあったが、ここは御簾が半分下がっていて、さすがにその奥は薄暗い。そこに佐為は入っていった。
「光、早くおいで」
「だれぞ!灯りを!」
佐為はまた奥に人を呼んだ。すると、今度は初老の舎人がやってきて、灯りを灯していった。
「ねぇ、佐為の屋敷ってさぁ。いったい、何人ひとがいるの?」
「え、下仕えしてくれている者たちのことですか?」
「うん。今のあの灯りを持ってきてくれた舎人が一人、そしてさっきオレに飲み物を持ってきてくれた女房が一人だろ・・・・?」
「それから、牛車を引かせる若い牛飼い童がもう一人おります。ま、他にも何人かおりますが・・・」
「ふーん。やっぱそんなもんだよなぁ・・」
「どうして?」
「だって佐為んちって、なんかいっつも静かでさ、人が居るんだか、居ないんだかって感じだけど、ちゃんとめしが出てきたり、それから、庭は草茫々だけど、家の中は綺麗になってるから、一応何人かはいるんだろうなぁって・・」
「まぁ、私一人ですし、あの者たちが居てくれれば私は充分なので。それに・・、今は光が来てくれているから、心強いです。若い舎人は今まで牛車の世話をしてくれる者が一人だけでしたからね」
と付け加えるのを忘れなかった。
よく見ると、今二人が居る間も趣味のよい上品な調度が置かれている。そこは塗篭という間で、いわゆる衣裳部屋のような場所である。
しかし、ここは佐為の寝所でもあった。中央には御帳台が置かれている。
帳台は畳二畳ほどのスペースに、四方に帳をめぐらし、天井に障子を乗せたものである。内側には几帳も立ててある。畳二畳の上にはさらに畳が重ねて置かれ、その上に褥(しとね)が整えられている。西洋のような高さはないが、幕の下がった天蓋付きの寝台といったところだろう。
ここには光も何度か泊まらせてもらっている。佐為の屋敷には客用の帳台がしつらえられていない。当然の成り行きで、佐為の帳台の中で光も横になるのだ。二畳分のスペースには小柄な光が入っても充分ゆとりがあった。
本来、正式には屋敷の主人は、このような衣装部屋などではなく、寝殿の中央に位置する母屋という広間に帳台をしつらえるのが本当だった。が、佐為は好んでこちらのこじんまりした空間を使っている。
その帳台の横に衣や着物の入った櫃がいくつか置いてある。黒い漆塗りに螺鈿が施された美しいものばかりだった。それを開けると、良い香りがふわりとこぼれ出る。
「さぁ、どれが良いでしょうね」
中から、佐為が白い単の着物を取り出すと、光に合わせてみた。
「ちょっと大きいようですが、まぁいいでしょう。さぁ、光。濡れた着物を脱ぎなさい」
「え、ちょ、ちょっと待って」
さっき、あんなに大胆に水干を脱ぎ捨てた光だったが、今度はさすがにもじもじしている。いくら薄暗い室内とはいえ、人前で肌をさらすのは光の歳ではもう恥ずかしいことだった。佐為は完璧にオレを子供扱いしている・・んだな。光はそう思った。赤ん坊じゃねえんだぞ。脱げったって・・・。単の着物は下着である。つまりそれを脱いでしまえばその下は何もつけていないのだ。
おまえの前で素っ裸になれってのかよ・・・・。
「ほら、何してるんです、早く光。本当にこんなに冷えてしまって、かわいそうに」
そう言って、佐為は両手で光の肩を包んだ。暖かい・・・。佐為のぬくもりが心地良い。
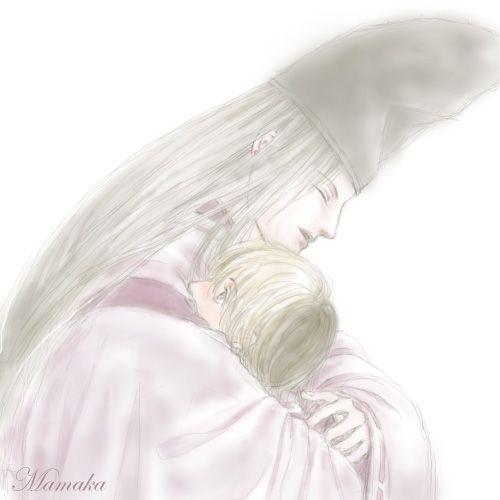
しかし、佐為が光の着物に手をかけようとした時、光は思わず口を開いた。
「い、いいよ、佐為。自分でやるから、それ貸して!」
と佐為を押しのけると、彼の持っていた単を奪い取り、傍にあった几帳に隠れてしまった。こんな仕草を見て佐為はやっと光が恥ずかしがっていることに気付いた。そして、そんな光を見ると、笑みがこぼれた。まるで我が子の成長に目を細めるように。
「じゃ、私は外に出てますから、着替えたら、来なさい、光」
佐為は、また簀子に出て、腰を降ろした。暗くなってきたとはいえ、やはり日のあるうちは簀子のほうが断然明るいのだ。だから、いつも光と簀子にいる。たくさん人が集まるのではやはり屋内に入るしかないが、光と二人で打つのであれば、碁も簀子で打つほうが断然気持ちが良い。
一陣の風が吹いてきた。
「寒っ。もう夏物の狩衣では肌寒くなってきましたね。そろそろ家でも直衣(のうし)を着る時期でしょうか・・」
佐為がそんな独り言を言っていると、屋敷の奥から情けない声が聞こえてきた。
「さ〜い〜。ダメだ〜・・・。来てよ〜〜〜」
「ど、どうしたんですか!?光」
佐為は慌てて、また御簾をくぐり、奥へ入っていった。
見ると、光は佐為の白い単の着物を肩にかけて、前を一応合わせているが、腰で結んだ帯がどうもへんな形をしていた。そして、佐為には腰丈ほどしかない着物も、光が着ると裾が膝下の方まできてしまっている。袖も光には長すぎるようだ。
「あははははははっ。光、なんですか!その格好。まるでお化けです」
「笑うな!もーっ。だってさー。やっぱおまえの着物じゃ大き過ぎなんだよ!。これじゃ袴はけないよ」
「どれ貸して御覧なさい。しょうがないから、おはしょりをしましょう」
佐為は光の結んだ帯を解くと、前をあわせ直した。
「光、腕を上げていて」
次におはしょりになる部分をつまみ、帯を腰に回す。当然この瞬間、ほとんど二人は抱き合ったような格好になる。佐為は長身である。光とはまだ頭一つ分の身長差があった。彼は、小さい光に合わせて腰をかがめている。佐為の髪が頬に掛かる。光は落ちつかなげに首を心持ち上に向けた。
「光は、細いですね。もうちょっと肉をつけてもいいかもしれません。あんなに食べているのに、どうして太らないんでしょう?」
佐為は自分の腕を光の脇の下から背中に回して帯を渡し、頬は触れ合うような近さになった。
「あ、またあの匂い。佐為、おまえの香いい匂い」
頬に触れる佐為の髪から、あのえもいわれぬ良い香りがした。
「そうですか?」
「うん。いつも佐為、この匂いがする」
「栴檀です」
「センダン?」
「そう。私の母上がよく焚いていた香なのです」
「へ〜」
「私はこれがとても好きで・・・、ただ高価なものですから。でも私が贅沢をするのはこれくらいですよ。良い匂いでしょう?」
「うん!なんていうか、こう花の匂いと違って甘たるいんじゃない。強すぎもしない。なんつーの、そこはかとなく・・・ていうか。品があって、す〜っと頭が冴えるような・・・・。なんて表現していいかわかんないよ。でもこれ、ずっと嗅いでたい。なんかそんな匂いだな。芳しい・・、ってこういうこと言うのかなぁ」
そう話している間に佐為は上手くおはしょりを作ってやった。
「どう、これでちょうど良いでしょう」
佐為はにっこり満足気に光を眺めた。
「あ、待って!佐為。離れないでよ」
おはしょりが出来て、自分から離れてしまった佐為を、光は慌てて自分の方へまた引き寄せた。
「何、光?」
「だっていい匂いなんだもん。佐為」
「そんなに好きですか?この香り」
「うん」
光は佐為の腕を掴んでその胸に顔をうずめた。佐為が離れて心残りに思ったのは、栴檀の香りのせいばかりではない。薄寒い屋内でこの彼のぬくもりが心地よかったからなのかもしれない。
「さぁ、でも早く衣を着てしまいましょう。本当に風邪をひいてしまいます。さ、指貫をつけて」
「うん」
光は今度は言われたとおりにした。指貫は自分のものである。手馴れた風に身につけ、先ほど脱いだ水干も着込んだ。水干を身につける時はまた佐為が手伝ってくれた。
「ねぇ、おまえさぁ、いつも狩衣を着てることが多いけど、それって自分だけで着れるから?」
「あ、よく分かりますね、光」
「なんだ、ほんとにそうなんだ」
「なんだ、ってどうして?」
「だってさ、この家、ひと少ないし、必然的に自分で着るしかないのかな、とか」
「えへへ。そうなんですよ。雇ってる下仕えの者があれだけなので、直衣(のうし)を着るのはちょっとね、大変で・・・。直衣もたくさんあるにはあるんですが。その点、狩衣は着るのが簡単ですから。あと、私は狩衣のほうが好きなのですよ。なんとなく」
「佐為さぁ、もうちょっとひと増やせばぁ?だって内裏に行く時はちゃんとした格好しないといけないだろ。おまえ、そんなに困ってんのか?」
遠慮のない物言いである。
「あ、ちゃんとした格好ってのは、ひとに着付けてもらわねばならない格好つーことだぜ。念のため。おまえ、べつにちゃんとしてることはちゃんとしてるからさ」
「あはははははっ。光、面白いですね。あなたは」
「今はね、困ってなどいませんよ。一応出世しましたから」
そう言って佐為は愉快そうに笑った。
「さぁ、簀子に戻りましょう、光。日が暮れる前に一局打ちましょう」
「うん」
二人は碁盤を挟んで向かい合った。
「光、私はね、宮中の雅な嗜みが嫌いではありません。歌も楽も、衣に趣向を凝らすのも、こうして香を選ぶのも、実はどちらかといえば好きです」
「そーだろうーなぁ。だっておまえ、何やってもそれなりに絵になってるし・・・。ま、蹴鞠だけはちょっと、何だけど・・・・。それにすげぇおしゃれだもんなぁ」
確かに、佐為は着物のセンスがよく、色の合わせも上手で、寂れた質素な屋敷に住んでいるとはいっても、身につけるものだけは上流貴族らしく常に良いものだった。それは手入れの行き届いた美しい髪からも窺える。佐為の優美で洒落た着こなしに対して、光は常に「動きやすさ」重視で衣を身に着けていたし、簡素なものが好みでもあった。
光は武官の家の子であったから、なおさらである。
「でもね、実を言うと、あなたが言うとおり、以前は暮らし向きが楽ではありませんでした。だから、あまり贅沢は出来なかったんです。ご存知のとおり、私は官職についておりませんでしたから、わずかに与えられた地方の領地から上るものだけが頼りでした。
雅なものは嫌いではありませんが、でもそれはあくまで碁の次に、ということです。宮中で官職を争って昇りつめることなど、何の興味ももてません。そのような暇があったら、碁の腕を磨きたい、私にはそれしかなかったんですよ。だから、このような気ままに見える暮らしをしてきたのです」
「じゃさ、なんで、ひとに囲碁を教えるわけ?おまえ、帝以外にも指導碁ってよくするだろ。 腕を磨くなら、ひとに教えてるどころじゃないんじゃないの?」
「光、あなたは昔の私を知りません。私はずっと碁の修行を重ねてきました。拠所とする師匠にも出会いました。自分より弱い者に囲碁を教えるのは、自分ひとりだけ、高みを極めてもそれでは何にもならないからです。神の一手はそのように自己完結のうちに為し得るようなものでは無いのです。決して」
「ふーん」
「それにね、光。私、教えるの大好きなんです」
佐為はとても幸せそうに微笑んだ。
「何故といわれても答えられませんが、指導碁を打つのは私にとってとても楽しいことなのですよ。もちろん、力の見合うものとの真剣な対局から得られる悦びとはまったく違うものですが・・。それとは別に、人に教えることに魅力を感じます」
「だから、オレともこうして毎日打ってくれるの?」
「ええ、そうですね、光はとても才能がありますから、教えるのがまた格別に楽しいです。あなたは私の一手が何を言わんとしているか、即座に悟り、私が導き出したかった次なる一手を、応えてくる。時には私が予想しなかった斬新な手で応えることもある。あなたの覚醒していく様が私をわくわくさせてくれるのです」
「ふーん、おまえはオレの蹴った鞠、ぜんぜん見当外れな方向に蹴り返すけどな」
二人は笑った。
佐為は・・・、やっぱりおしゃべり・・・だな。と光は思った。
頬が高揚している。瞳が輝いている。このように生き生きとした佐為を眺めるのは光にとっても幸せな気分を運んできてくれた。
目の前に座る佳人は姿形ばかりが美しいのではないと、心から思った。
このひとの心はその外見以上に美しいのだ。
こんな幸福な時間が永遠に続けばいい、光はこの時心からそう思った。
つづく
back next
|